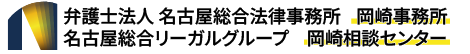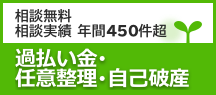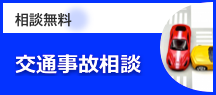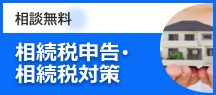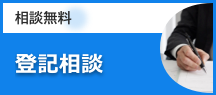1. 遺留分減殺請求とは

(1)遺留分とは、相続人に法律上留保されなければならない一定の割合をいいます。
遺言書で特定の相続人のみに遺産を承継させる内容になっている場合や、被相続人が生前に特定の相続人に多額の財産を贈与していた場合等に問題となる可能性があります。
(2)遺言書の内容を把握できていない場合には、次のように対応することが可能です。
遺言書が公正証書遺言の場合には、公証役場で原本が保存されていることから、相続人は謄写申請をすることが可能です。
自筆証書遺言の場合、通常は検認手続きをしています。検認手続きを経ている場合には、家庭裁判所に対して検認調書の謄写申請をすることが可能です。
相続人間で対立が大きく、対立している相続人が遺産を全て承継する内容になっている場合、遺言書の内容を知らされることなく、当該相続人により相続手続きが進められているケースが多くあります。このような場合には、早期に遺言書の内容を確認し、遺留分減殺請求が可能か検討するべきでしょう。
2. 遺留分権利者と割合
(1)権利者
遺留分権利者は、兄弟姉妹以外の相続人です(民法1042条)。具体的には、配偶者、子、直系尊属です。
(2)割合
① 直系尊属のみが相続人である場合 被相続人の財産の3分の1
② ①以外の場合 被相続人の財産の2分の1
3. 遺留分侵害額
(1)遺留分を算定するための財産の価額(1043条)
① 被相続人が相続開始の時に有した財産の価額
+(加算)
② 贈与財産の価額
-(控除)
③ 被相続人の債務の全額
※ 遺留分を算定する前提として、①相続開始時点の財産及び②贈与財産の調査が必要となります。この点は、4以下で述べます。
(2)個別的遺留分の割合
個別的遺留分は、2で述べた遺留分の割合に法定相続分を乗じた割合です(1042条2項)。
(3)遺留分侵害額
(1)及び(2)から算出される遺留分額から、遺留分権利者が受けた贈与又は特別受益の額と遺留分権利者が相続によって取得すべき財産の額を控除し、遺留分権利者が承継する相続債務の額を加算して求めます(1046条)。
4. 財産調査
3で述べたとおり、遺留分を算定するための財産の価額を算出するにあたっては、①被相続人が相続開始の時に有した財産の価額及び②贈与財産の価額を把握する必要があります。
(1)①相続開始の時に有した財産の調査
典型的なものとしては、
❶不動産、❷預貯金、❸現金、❹有価証券、❺動産 等があります。
❶不動産の調査にあたっては、被相続人の死亡した年の名寄帳の取得をするとよいでしょう。
不動産が特定できれば、現況を確認し、不動産の登記情報も取得するとよいでしょう。被相続人の死亡後、遺言書で承継していた特定の相続人が売却手続きを進めている可能性があります。
❷預貯金の調査にあたっては、金融機関が分かっていれば、当該金融機関で死亡時点の残高証明書の取得をすることになります。
判明している以外の預貯金がありそうな場合には、地銀や主要銀行に対して預金照会を行い、口座の存在が確認できれば同じく残高証明書を取得することになります。
❸現金の調査にあたっては、被相続人の自宅内、金融機関の貸金庫内等に保管されている可能性があります。被相続人の通帳の履歴から、貸金庫の金庫代金が引き下ろされている場合には、貸金庫を契約している可能性が高いといえます。
❹有価証券の調査にあたっては、証券会社に対して残高証明を行うことになります。有価証券があるかどうか分からない場合でも、被相続人の通帳の履歴をたどる中で、配当金や利息の記載から有価証券の存在が推知できることもあります。
❺動産の調査にあたっては、高価品等が貸金庫等に入っている可能性があります。
(2)②贈与財産の調査
被相続人が生前贈与をしていた場合には、遺留分算定の基礎となる財産に算入できる可能性があります。問題は、被相続人と長い間交流がない等生前の事情を把握できないような場合にどのように調査するかです。
不動産については、過去分の名寄帳を取得し、不動産の登記情報を取得します。売却がされている場合には、所有者が変更されている可能性があります。
預貯金については、金融機関に対して過去数年分の取引履歴の開示を求めるべきです。金融機関により開示可能な期間は異なりますが、長期で10年分が取得できることが多いです。通帳の記載から、他の相続人への送金の履歴や出金の履歴が出てくる可能性があります。また、不動産等の売却代金が記載されている可能性もあります。
その他に、被相続人の生前の日記やメモ等から生前贈与に関する情報を得られる可能性もあります。
5. 手続き
遺留分減殺請求の時効期間は、「相続の開始及び留分を侵害する贈与又は遺贈があったことを知った日から一年間」(1048条)です。
時効期間が1年間と短いため、遺留分が生じている可能性がある場合には、早急に相手方へ遺留分減殺通知書を相手方へ送付するべきです。遺留分減殺請求権を行使した日を特定できるよう、配達証明付内容証明郵便により送付することが通常です。
遺留分減殺請求の解決にあたっては、①協議→②調停→③裁判という流れを経ることになります。
なお、被相続人が認知症に罹患している時期に遺言書が作成された等、遺言書の有効性に疑義がある場合には遺言の有効性を争うことも考えられます。
遺言書の有効性を争う場合には、遺言無効確認請求訴訟を提起することになります。
当該訴訟で遺言書が無効と判断されれば、それを前提に遺産分割協議をすることが可能ですが、遺言書が無効ではないと判断されれば、遺言書の内容通りに相続がされてしまいます。
遺言無効確認請求訴訟に遺留分減殺請求の意思表示は含まれないとされています。
そのため、遺言無効確認の決着がついた段階では遺留分減殺請求の時効期間が経過している可能性があります。
したがって、遺言書の無効を主張する場合であっても、遺言書が有効であると判断された場合に備えて、遺留分減殺請求の意思表示はしておくべきです。