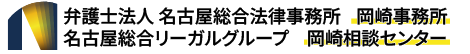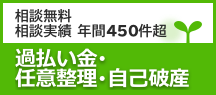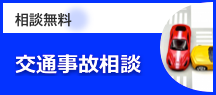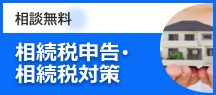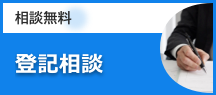| Q | 会社役員が交通事故にあった場合の休業損害・逸失利益はどのように算出されるのでしょうか。 |
|---|
| A | 役員報酬のうち労務対価部分を基礎収入として休業損害・逸失利益を算出することになります。 |
|---|
【解説】
1.問題点
交通事故にあったことにより仕事を休んだ場合は休業損害、さらに後遺障害を負った場合は逸失利益を請求することができます。
いずれも、被害者の基礎収入を基礎として算出されます。
もっとも、役員報酬の場合、労務対価部分としての報酬の他に、経営者としての会社の利益配当部分もあることもございます。
そのため、「役員報酬のうちのどの部分を基礎収入とするか」が争いになることが多くあります。
2.労務対価部分が基礎収入となること
この点、判例(最判昭和43年8月2日民集22巻8号1525頁)では、企業主の逸失利益に関して
企業主が生命もしくは身体を侵害されたため、その企業に従事することができなくなったことによって生ずる財産上の損害額は、
原則として、企業収益中に占める企業主の労務その他企業に対する個人的寄与に基づく収益部分の割合によって算定すべきである。
企業主の死亡により廃業のやむなきに至った場合等、特段の事情の存しないかぎり、
企業主生存中の従前の収益の全部が企業主の労務等によってのみ取得されていたと見ることはできない。
したがって、企業主の死亡にかかわらず企業そのものが存続し、収益をあげているときは、従前の収益の全部が企業主の労務等によってのみ取得されたものではない。
と推定するのが相当である。
として、企業主の逸失利益に関して、原則として労務対価部分が対象となると判断しました。
そのため、役員についても同様に、役員報酬の内労務対価部分が基礎収入となるものと解されています。
そして、労務対価該当性の有無は、
会社の規模・利益状況、
当該役員の地位・職務内容・年齢、
他の役員・従業員の職務内容・報酬・給与額、
事故後の報酬額の推移等
を考慮して判断されています。
3.裁判例
⑴ 東京地判平成15年3月27日・交民36巻2号439頁
- 会社役員の死亡逸失利益
- 給料月額110万円→全額認定(ただし4年間)
- 内容
被害者が
いわゆる雇われ社長であって、その収入は、役員報酬ではなく、全額が労働の対価である給与であったこと、本件事故直前3か月間をみると、その月収は110万円であったこと
として基礎収入を月額110万円全額と認定しました。
もっとも、前任者の任期期間が比較的短期間であったことから、「被害者の任期は66歳までの4年間とみるのが相当である」として、4年間についてのみ給与全額の月額110万円を基礎収入としました。
そして、66歳以降の就労可能期間については、65歳以上大卒男子労働者の平均賃金を基礎収入として判断しました。
⑵ 名古屋地判平成15年1月17日・公民36巻1号49頁
- 会社代表取締役の逸失利益
- 役員報酬年収360万円→全額認定
- 内容
被害者(原告)は、
役員報酬として一か月あたり30万円(年間360万円)の支払を受けていた
が、交通事故にあった年度は270万円しか受けていない。これは、
本件事故により傷害を負ったことから、事故後の3か月間の報酬90万円の支給を受けられなかったことが原因であると推認される。
これによれば、
原告が本件事故後にも1か月あたり30万円(年額360万円)の収入を得られた蓋然性が高いと考えられ、そうすれば、原告の逸失利益の基礎となる年収は360万円とするのが相当である。
として、被害者の役員報酬全額を基礎収入として認定しました。
⑶ 千葉地判平成25年6月5日・自保ジャーナル1908号159頁
- 会社代表者の逸失利益
- 役員報酬1,826万7,660円→全額認定
- 内容
原告会社は、
持ち株比率が原告X1が50%、
常勤取締役である妻が30%、
常勤取締役であるAが10%の同族会社である。
原告会社は代表取締役である原告X1のほか、役員2名、正社員4名、パート2名で構成されている。
本件事故直前の21期の役員報酬は、
・原告X1は1,826万7,660円
・妻は615万8,160円
・Aは803万6,000円
・非役員で最も給与の高いBは平成23年度給与586万8000円
である。
原告X1は、社員らの中で最も長時間勤務していた。
その役割は、
・社長として業務全体を統括
・業務全体の進行状況の把握
・社員の業務日報の確認等の労務管理
・経理の確認
・その他書類の決裁
・施工部のリーダー
・施工現場の監督
加えてもともとが原告X1の個人事業を法人成りさせた関係上、営業活動でも原告X1自身が直接担当する顧客があった。
売上比率でいえば営業のリーダーであるAと比べて遜色なかった。
上記21期と本件事故直後の22期を比較すると、売上高、売上総利益、損益がいずれも低下ないし悪化した。
原告X1は、Aと比べて、社長としての役割の他に、施工・営業部門を通じてみた場合により大きな働きをしている。
Aの2倍強(Aの報酬は上記Bとの対比において全額が労務対価部分と認められる。)の、上記Bは施工・営業部門のリーダーとしての役割を有しない。
このことから、同人の3倍強の、各労務提供をしているものと解される。
原告X1の上記報酬が労務の対価としてAや上記Bの報酬や給与と均衡を欠いているということはできない。
また、原告会社の法人税率と原告X1の所得税及び住民税の税率を考慮すると、法人税の圧縮のために報酬を加算するとも考えにくい。
よって、原告X1の役員報酬は全額が労務対価部分であると認められる。
⑷ 東京地判平成18年5月26日・交民39巻3号698頁
- 会社代表者の休業損害及び逸失利益
- 給与1,128万円→65%の733万2,000円を認定
- 内容
原告会社の役員の構成、その出資者の構成を見れば、原告会社は同族会社と認められる。
原告Aは本件事故前、
・職人の差配
・現場監督を行う
・自ら鳶職として現場作業にも従事
していた。
本件事故により休業したため、平成14年9月から平成15年6月までは給与の支給を受けていない。
復職後も、本件事故により現場監督及び鳶職としての稼働が不可能になったため、給与が年額780万円に減額している。
原告Aの休業期間中、原告Aが行っていた職人の差配、現場監督等の仕事は、Eが行っている。
Eの本件事故前の給与は年額583万9,915円である。
原告Aの代わりに職務を行ったことによる加給金額は月額5万円にすぎない。
原告会社の売上、営業利益及び当期利益は、本件事故前、原告Aの休業期間中及び原告Aの復職後を通じて大差がない。
原告Aの休業期間中の原告会社における人件費も216万9,070円増額しているにすぎない。
以上のことなどを考え併せれば、原告Aの原告会社の給料における労働の対価部分は、その65パーセントの年額733万2000円と考えるのが相当である。
として、給与の65%を基礎収入として認定しました。
4.さいごに
以上のように、役員の休業損害、逸失利益の算出にあたっては基礎収入額が争いとなります。
報酬・給与のうちの労務対価部分がどの程度であるか、きちんと立証する必要があります。
労務対価部分の認定にあたっては会社の事情、当該役員の事情、他の役員・従業員の事情等様々な要素が考慮され、通常のサラリーマンの場合と比べて立証が難しい面があります。
そのため、役員の方が交通事故に遭われた場合には早期に弁護士に相談されるのがよいかと思います。