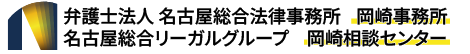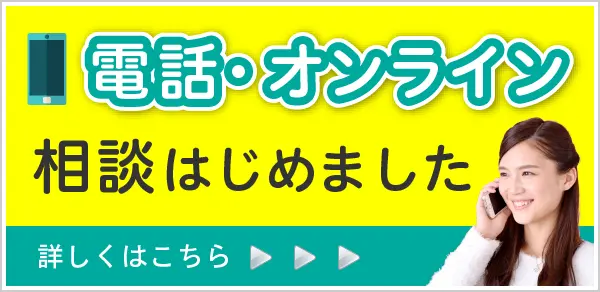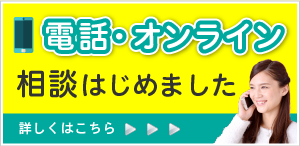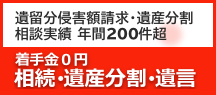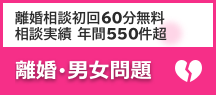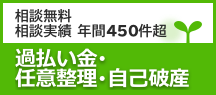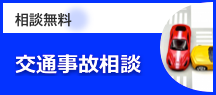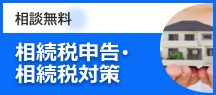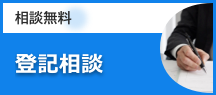ご相談者様の状況・ご相談内容
- 依頼者:Aさん(30代女性、パート・無職)
- 相手方:Bさん(夫)
- 婚姻期間:約3年、別居期間:約2年
- 離婚の種類:調停離婚
- 子ども:あり
解決内容
面会交流調停の取下げ、解決金の受領、相場より高い養育費の決定
事案
Aさんは、出産のための里帰りをきっかけに実家で子どもと暮らしていました。出産以降は、Aさんの体調が悪いこともあり、実家と夫と住んでいたアパートを行ったり来たりする生活をしていました。
やがて、夫からアパートでAさん、夫、子どもの3人で住むことを持ち掛けられましたが、夫の言動に対するストレスから、Aさんの体調に異常をきたすようになっており、すぐに同居することは難しい旨を伝えました。
それを受けた夫から離婚を切り出されました。Aさんが、離婚に応じる考えはあるが、新しい環境の準備が整うことを待ってほしいことを伝えると、夫は代理人(弁護士)に依頼し、Aさんを相手方として離婚調停を申し立てました。
また、Aさんは、夫とLINEを用いたやりとりをし、定期的に夫と子どもが面会する機会を設けてきましたが、面会の打診をしたところ返事がないまま、離婚調停を申し立てられました。
離婚調停を申し立てた段階で、夫は子どもと面会をする機会を求めていましたが、これまでAさんは夫と子どもが面会できるよう取り計らってきており、返事がないまま調停を申し立てられたのに、まるでAさんが一方的に面会を認めないかのような主張され、困惑していました。
担当弁護士は、離婚調停への対応を受任しました。
弁護士の対応
1. 初期の対応
離婚調停を申し立てられた場合は、「申立の実情」と題する書面において、離婚調停を申し立てるに至った経緯が書かれていることがあります。
本件も、夫の代理人が「申立の実情」と題する書面において、離婚調停を申し立てるに至った経緯を記載していました。
しかし、この内容がAさんから見た事実と異なっている点が多かったため、Aさんからみた別居に至った経緯や、これまでの夫とのやりとりを「答弁書」に記載して提出し、改めて、早期の離婚に応じられない旨を伝えました。
2. 面会交流調停への対応
その後、夫は離婚調停係属中に、面会交流調停を申し立てました。
Aさんはこれまで夫と子どもの面会の機会を設けてきたのに一切Aさんが面会を認めてこなかったかのような主張をされ、夫に対する信頼を失い、体調にも異常をきたしていました。
担当弁護士は、
面接交渉(直接面会)の可否については、婚姻前後の申立人、相手方及び未成年者らの関係、未成年者らの意向等の諸般の事情を踏まえ、面接交渉が未成年者の成長に及ぼす影響、監護親と未成年者との関係に及ぼす影響等を総合的に考慮して、子の福祉に合致する場合にのみ面接交渉を認めるのが相当というべきである
とした東京家裁八王子支部平成18年1月31日審判を引用し、Aさんの現状、これまでの夫との関係、子どもの現状等を書面に詳しく記載し、現在、面会交流に協力することは難しい旨を主張しました。
また、東京高決平成2年2月19日を参考に、別居親を親と認識していない幼い子供との面会交流には、監護親(同居親)の協力が不可欠であるが、協力できる状況にはないことも主張しました。
その結果、夫は面会交流調停の申立てを取り下げました。
3. 離婚調停の決着
調停の場で、夫は、離婚に早期に応じないのであれば、調停を不成立とし、訴訟を提起することを主張しました。訴訟になってもすぐに離婚が成立するものではないので、離婚を先延ばしにしたくないという意思表示と考えられました。
早期の離婚は、Aさんにとっても有利になる事情がありました。養育費は、当事者双方の前年の年収と子の年齢、数に基づいて決められます。Aさんは、昨年の年収よりも今年の年収の方が上がることが考えられたため、早期(年内)に離婚に応じたほうが、養育費の額が高い金額で決まる可能性がありました。こちらは、解決金の支払と、養育費を相場より高い金額で合意ができるなら、早期の離婚に応じる意思を示しました。
次の回の調停で、解決金の額と、養育費の額の歩み寄りがされ、離婚調停が成立しました。
担当弁護士の所感
本件では、申立人である夫が早期の離婚を望んでいたため、当方に有利な条件を呑んでもらうことができました。
また、Aさんが状況や経緯を時系列に沿って具体的に教えてくださったため、説得的な主張を書面に記載することができました。
- 本件のポイント
- 相手が早期の離婚を求めている場合は、当方に有利な条件を提示して早期離婚に応じるのもあり。
- 面会交流の実施については、監護親の状況も重要な要素になる。
参考裁判例(東京家裁八王子支部 平成18年1月31日審判)
面接交渉(直接面会)の可否については、婚姻前後の申立人、相手方及び未成年者らの関係、未成年者らの意向等の諸般の事情を踏まえ、面接交渉が未成年者の成長に及ぼす影響、監護親と未成年者との関係に及ぼす影響等を総合的に考慮して、子の福祉に合致する場合にのみ面接交渉を認めるのが相当というべきである