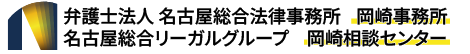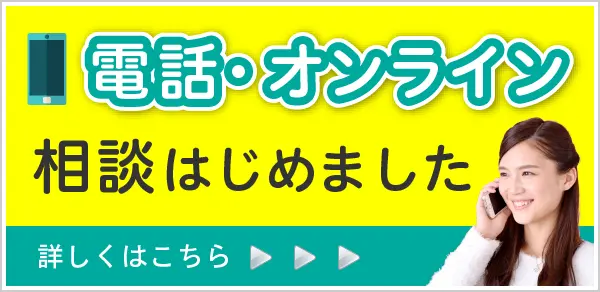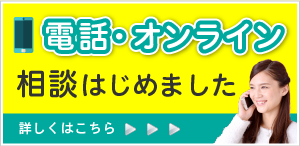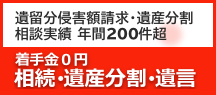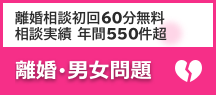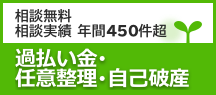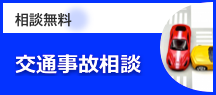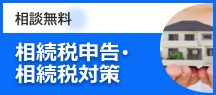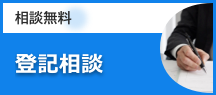1.はじめに
西三河弁護士会では、法教育の一環として、複数の弁護士が中学校へ行き、実際の刑事裁判に近い模擬裁判を実施する出張授業を毎年行っています。
岡崎事務所所属の弁護士も毎年出張授業を行っているため、今回はその様子をお伝えします。
2.模擬裁判とは?
模擬裁判とは、弁護士会が用意した刑事事件の台本を用い、以下の役割を中学生自身が担います。
・検察官(起訴をして有罪を求める立場)
・弁護人(被告人の立場を守る役割)
・裁判官(証拠や証言を総合的に考慮して判断を下す役割)
・被告人(事件の当事者)
・目撃者(事件の様子を証言する立場)
台本には、一連の裁判の流れが記載されているほか、複数の証拠資料が添付されています。今回の事案は、コンビニ強盗犯が逃走し、付近の住宅に住んでいる住民が犯人として逮捕されましたが、その人物が、コンビニ強盗犯と同一人物であるのかが争われました。
3.証拠をもとに有罪か無罪かを考える
模擬裁判の大きなポイントは、「本当に犯人であったのかを、証拠に基づいてどう判断するか」という経験を積むことです。模擬裁判では、各チームに分かれて、証拠に基づいて有罪・無罪の意見を話し合いが行われました。各チーム有罪・無罪で意見が分かれる場面も多く、白熱した議論が繰り広げられました。
裁判官チームは、最終的に判決を出さなければなりません。また、台本には、有罪、無罪のどちらのパターンの判決も掲載されているため、実際にどちらを選択するのかは、裁判官チームにゆだねられています。
4.判決
裁判官チームによる主文の朗読と、今回の判決に至った理由として、どのような証言や、証拠が重視されたのか、また、被告人の主張と証拠との整合性をどのように考えたのかを発表してもらい、模擬裁判は終了しました。
5.判決後の弁護士からの解説
判決後は、弁護士が台本の事件を解説し、なぜその証拠が重要になるのか、弁護士であれば、どのように考えるのか、実際の事件であれば、他にどんな証拠が必要になるのか等々が解説されました。また、中学生の皆さんからの鋭い質問も多く出て、弁護士も感心させられる場面が多くありました。
6.模擬裁判を通じて
実際の裁判でも、模擬裁判で行われたことと同様に、裁判官が証拠に基づいて被告人が犯人であるか否かが争われることがあります。模擬裁判で重要なことは、結論が正しいか否かではありません。正直、弁護士が作成している架空の事例であるため、決定的な証拠や、本来であれば収集されているはずの証拠等は出てきません。つまり、結論を出すのが非常に難しくなるように作られているのです。重要なのは、論理的に証拠を検討し、結論を出すということになります。模擬裁判は、ニュースや教科書だけではわからない裁判の仕組みや論理的に物事を判断する大切さを体験できる機会であり、模擬裁判を通じて、中学生の皆さんが「証拠に基づいて考え、論理的に判断する」経験を提供したいと考えています。