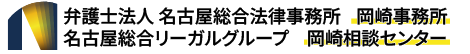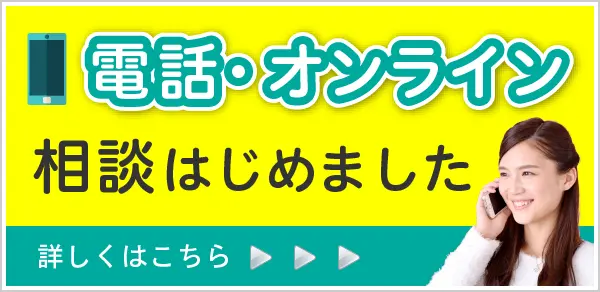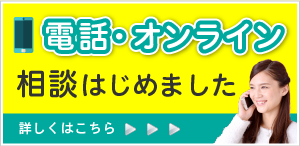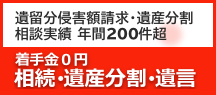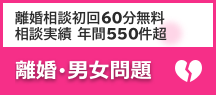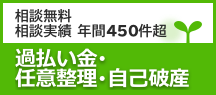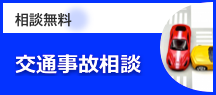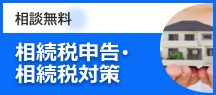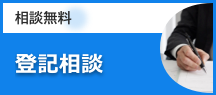1.はじめに
令和6年5月24日に成立した民法等改正法にて、「法定養育費」制度が新設されました。今回は、「法定養育費」制度の概要について、ご説明いたします。
なお、同法律は、令和8年5月までに施行される予定ですが、本記事執筆時点(令和7年2月28日)では、施行日は未定です。
2.「法定養育費」新設の経緯
現行民法では、父母が離婚する際、養育費の額を協議や調停等によって定める旨の規定はありますが(民法766条)、協議離婚する際、離婚届には養育費の金額等を記載する欄がないため、事実上、養育費の額等を定めることなく離婚するケースがあります。
このような場合、離婚後に当事者間で協議を行うか、調停、審判等で養育費の金額を定める必要がありますが、かなりの労力がかかるというデメリットがありました。
そこで、新設された規定が「法定養育費」になります。
3.「法定養育費」とは
「法定養育費」とは、父母が養育費の額を定めることなく協議離婚した場合、子を監護している側は、元配偶者に対し、法務省令で定める一定額について、協議等を経ることなく請求することができるものになります(改正民法766条の3)。
(1)請求できるための要件(条件)
条文上、「父母が子の監護に要する費用の分担についての定めをすることなく協議上の離婚をした場合」と規定されているため、①協議離婚していること、②離婚時に養育費についての取り決めをしていなかったことが要件となります。
(2)いつから請求できるのか
「離婚の日から」請求することができます。他方、本法律には遡及効がないため、本法律が施行されるより前に離婚していた場合には、適用されないことに注意が必要です。
本記事執筆時点(令和7年2月28日)では施行されていないため、同法律が成立後に離婚した方が対象となります。
(3)いつまで請求できるのか
以下の①から③のうち、いずれか早い日までの間、請求することができます。
①「父母がその協議により子の監護に要する費用の分担についての定めをした日」
②「子の監護に要する費用の分担について審判が確定した日」
③「子が成年に達した日」
同条文は、あくまで当事者間で養育費の額等を協議するまでの間、暫定的な養育費を確保するための規定であるため、協議等で定める養育費の終期は、③「子が成年に達した日」となるわけではないことに注意が必要です。
(4)いくら請求できるのか
条文上、「父母の扶養を受けるべきこの最低限度の生活の維持に要する標準的な費用の額その他の事情を勘案して子の数に応じて法務省令により算出した額の支払を請求することができる」と定められています。本記事執筆時点(令和7年2月28日)では、法務省令の定め等の公表がないため、請求できる金額は不明です。
また、請求された側は、「支払能力を欠くためにその支払をすることができないこと又はその支払をすることによってその生活が著しく窮迫することを証明したとき」は、「その全部又は一部の支払を拒むことができる」との規定もあるため、請求されたら必ず一定額の支払い義務が生じるとまでは言えないことになります。
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00357.html)
4.おわりに
民法(家族法)の法改正がなされ、離婚に関する運用等が大きく変更されることになります。離婚をお考えの際は、離婚する前に一度、専門家へ相談されることをおすすめいたします。