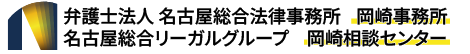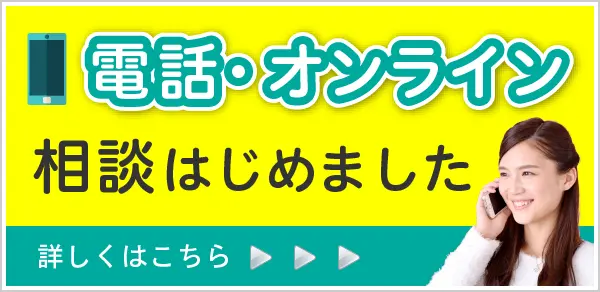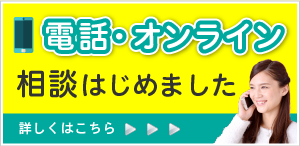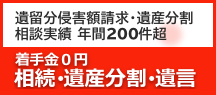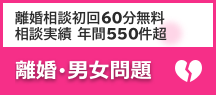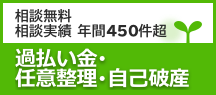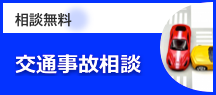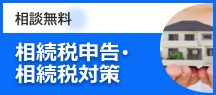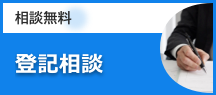1.岡崎支部でのウェブ調停
令和6年12月、私が名古屋家庭裁判所岡崎支部で開かれた離婚調停に出席すると、調停室に大きなモニターが置かれていました。調停委員は、「相手方はウェブで参加しています。」と言いました。
裁判所に来なくても、遠方からアプリを用いたオンラインの対話で調停に参加できるウェブ調停は、令和3年12月から東京、大阪、名古屋、福岡の家庭裁判所で試行的に始まりました。岡崎支部は最近まで裁判所外から調停に参加する場合の手段は電話のみだったのですが、ついに岡崎でもウェブ調停が始まったのか……と感じました。
ウェブ調停で利用されているアプリはCisco Webexアプリでした。相手方と画面越しに会話する機会がありましたが、相手方の表情も良く見え、声もはっきり聞こえました(なお、このときは諸事情で相手方と話す機会がありましたが、調停においてはあまり相手方と直接話す機会はありません。)。
私も、名古屋家庭裁判所岡崎支部以外の裁判所での調停に電話で参加をしたことがあります。電話での参加ですと、調停委員の表情が見えないため言葉のニュアンスがわからないこともありました。しかし、ウェブであればその心配も少なくなると感じました。
ただ、裁判所か参加者側のどちらかの機器の調子が悪くなれば、結局は電話で参加することになります。
電話やウェブで調停に参加できるのは法律に根拠があるからです。家事事件手続法54条1項、258条1項は「当事者が遠隔の地に居住しているときその他相当と認めるとき」に「家庭裁判所及び当事者双方が音声の送受信により同時に通話をすることができる方法」によって調停に参加することを認めています。この「当事者双方が音声の送受信により同時に通話をすることができる方法」に電話とウェブが含まれると解釈されているのです。
2.ウェブ調停と調停成立
もともと、電話調停であってもウェブ調停であっても、離婚調停の成立をすることはできず、調停が成立する見込みがある場合は、裁判所に行く必要がありました。
しかし、令和7年3月から、ウェブ調停でも離婚調停が成立できるようになりました。令和7年3月から施行される家事事件手続法268条3項但書により、「家庭裁判所及び当事者双方が映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法による場合」は、離婚調停を成立させることができるようになったためです。電話調停での離婚調停の成立はできないままです。
3.改正による業務への影響
今までは、離婚調停を成立させる場合、遠方の裁判所であっても現地に行くか、「調停に代わる審判」にしてもらう必要がありましたが、依頼者の方が、ウェブ調停により調停を成立させても構わないのであれば、弁護士事務所と裁判所をウェブでつないで調停に参加し、成立させることができるため、遠方の裁判所が管轄であっても気兼ねなくご依頼いただけるようになりそうです。
この流れは、他の事務所様も同様かもしれません。
それでは、たとえば愛知県の方が、東京や大阪など遠方の弁護士に依頼しやすくなるか、というと、そういうわけではないように思います。
なぜなら、調停は原則、本人の出頭が必要であるため、弁護士にすべて任せる、ということができないためです。弁護士事務所からウェブ調停に参加する場合は、依頼者様ご本人も弁護士事務所に行き、弁護士とともにウェブ調停に参加する必要があります。愛知県の方が、調停のたびに東京や大阪の弁護士事務所に行くのは大変です。
調停が実施される家庭裁判所の近くの事務所よりも、自身が普段からアクセスしやすい事務所に依頼する流れが強まるのではないか、と考えました。